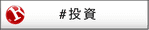初心者必見!バリュー投資家のための投資チェックリスト完全ガイド
作成日: 2025年01月11日
更新日: 2025年01月11日
バリュー投資の成功には、徹底した投資判断が欠かせません。とはいえ、初心者にとっては、どこから手をつけたらいいのかわからないことも多いですし、完璧に調査したと思っても調査漏れが生じてしまうこともありますよね。
そんなときは、投資チェックリストを利用すると、より良い投資判断ができるようになるでしょう。
この記事では、私いがらしが利用している投資チェックリストを紹介します。
投資チェックリストとは?
投資チェックリストは、企業分析の過程で重要なポイントを体系的に整理したツールです。これを使うことで、企業の事業内容や財務状況、株価の適正性を効率的に評価できます。
今回紹介するチェックリストは、以下を重視しています。
- 事業への理解
- 事業の収益性
- 事業の成長性
- 事業の財務
- 株価について(バリュエーション)
バフェット流のバリュー投資では、いきなりバリュエーションは行わず、まず事業内容や収益性、成長性、そして財務分析を行ってから、株価の適正性を判断します。
そのため、今回紹介するチェックリストは、この順番でチェックしていきます。
事業への理解について
バリュー投資の第一歩は、事業の理解です。自分が理解できないビジネスに投資することは、失敗を招きやすくなります。このセクションでは、以下のよう自問を通じて事業理解を深めます。
- 自分は、その会社の事業を理解しているか?
- その会社の事業は簡単に理解できるほど単純か?
こういった質問を自分に対して投げかけることで、事業内容を理解することができます。
事業の収益性について
事業の収益性を理解することは、バリュー投資において重要なステップです。いくら魅力的な事業でも、十分な利益を生み出せなければ、長期的に投資のリターンを得ることは難しくなります。このセクションでは、収益性の指標を確認しながら、投資対象としての適性を見極めていきます。
以下のチェックポイントを確認しましょう。
-
過去10年一貫して粗利率は40%を超えるか?
高い粗利率は、商品やサービスに競争力があることを示します。安定した高い粗利率は、経済的な堀(競争優位性)の証拠とも言えます。 -
過去10年一貫して純利益率は20%を超えるか?
純利益率が高い企業は、効率的なコスト管理ができている証拠です。収益性の高さは、事業の強固さを裏付けます。 -
過去10年一貫してROIC(投下資本利益率)は15%を超えるか?
ROICは、企業が投資した資本をどれだけ効率的に運用しているかを示します。高いROICを維持できる企業は、株主価値を持続的に増加させられる可能性が高いです。 -
その会社の事業は、多額の研究開発費を必要としていないか?
多額の研究開発費は収益を圧迫する可能性があります。特に、研究開発が成功しなかった場合のリスクを考慮する必要があります。 -
その会社の事業の販管費は、粗利の30%以下か?
販管費(販売管理費)が粗利を圧迫している場合、収益性が低下します。効率的な運営が行われているかを確認しましょう。 -
その会社の事業の減価償却費は、粗利の7%程度か?
減価償却費は設備投資の負担を示す指標です。粗利に対して適切な水準であることが理想的です。 -
その会社の利払いは、営業利益の15%以下か?
借入金の利払いが営業利益を圧迫していないかを確認します。健全な財務体質を持つ企業は、収益性の維持が期待できます。 -
その会社のROE(株主資本利益率)は30%以上か?
高いROEは、企業が株主資本を効率よく運用している証拠です。優れたROEを維持する企業は魅力的です。 -
その会社のROA(総資産利益率)は高いか?
ROAは、企業が資産をどれだけ効果的に活用しているかを示します。他の指標と合わせて分析しましょう。 -
過去10年一貫してCapEx(資本的支出)は純利益の50%以下か?
資本的支出が過剰だと、事業の持続的な収益性が疑わしくなります。過去の傾向を確認しましょう。
これらの質問を通じて、企業が持続的に利益を生み出す能力があるかを判断することができます。特に、過去10年の実績が安定している企業は、長期的な投資対象として検討する価値があります。
事業の成長性
事業の成長性は、長期的な投資リターンを左右する重要な要素です。収益性が高いだけでなく、安定した成長を続ける企業に投資することで、さらなる価値の拡大が期待できます。成長性を評価するためには、企業の過去の実績や市場でのポジションを確認しながら、将来の可能性を見極める必要があります。
事業の成長性を評価するポイント
事業の成長性を判断するために、**フリーキャッシュフローの直近10年のCAGR(年平均成長率)**に着目してみましょう。
フリーキャッシュフロー(FCF)は、企業が株主に還元できる余剰資金を示します。この数値が10年間で安定して成長していることは、事業の持続的な成長を裏付けます。フリーキャッシュフローのCAGRが15%以上であれば、高い成長性を持つと判断できるでしょう。
なぜフリーキャッシュフローのCAGRが重要なのか?
フリーキャッシュフローは、経営の効率性と健全性を示す重要な指標で、バフェットが言うOwner's Earningsnに近い概念です。この数値が高いほど、会社が本業で稼げていることを意味します。 フリーキャッシュフローの成長率が高い企業は、概して将来性が高く、株価の上昇を期待できます。
経営陣について
投資判断にあたり、会社の経営陣が一番重要と言っても過言ではないでしょう。 経営陣の手腕を見るにあたり、定性的な側面が重要になります。
特に以下が重要です。
- 経営陣は株主の還元に積極的か?
- 経営陣は継続的に自社株買いをしているか?
- 経営陣は他企業の後追いばかりしていないか?
- 経営陣は理性的な経営をできているか?
通常、経営陣が行う株主の還元とは、「自社株買い」「負債の返済」「「配当金の支払い」などがあります。 その中でも一番株主のためになるのは「自社株買い」です。 負債の返済も有効です。負債を返済することで、企業の財務体質が強化され、経営の安定性が高まります。 一番有効でないのが「配当金の支払い」です。 配当金は重視されがちですが、配当金は株主にとって税金がかかります。 (アメリカでは10%, 日本では20%) そのため、あまり効率的ではないのです。本来、配当金を支払うぐらいならば、自社株買いや負債の返済、事業への投資をするべきなのです。 ただし、企業の自社株買いが理知的であるか確認する必要はあります。自社株買いは、株価がバリュエーションより著しく安く、かつ、企業の財務体質が健全である場合にのみ行うべきです。この条件が揃わない場合、経営者は理知的な経営をしていないかもしれません。
次に、経営陣が他企業の後追いばかりしていないかを確認します。バフェットは他社の後追いばかりしている企業のことをレミングズ (Lemmings) と呼びます。他社の後追いばかりしていると差別化できませんし、いずれは価格だけで競い合うことになります。価格競争ほど企業の競争優位性を損なうものはありません。
これらを確認しておけば、経営者の手腕を見極めることができるでしょう。
財務について
財務については、以下のチェックポイントを確認しましょう。貸借対照表を確認します。
- 現金に対して負債はどれくらいあるか?
- 負債/自己資本が0.8以下か、すなわち自己資本比率が55%以上か?
- 現金に対して流動負債はどれくらいあるか?
- 長期負債はどの程度あるか?
- 自社株(Treasury stock)はあるか?
- 固定資産は小さい方が望ましい。固定資産はどの程度大きいか?
- 優先株 (preferred stock)はないか?
ここでみているのは「安全性」もしくは「財務健全性」です。 本当によい企業というのは、負債が少ないものです。 (金融業などは別です)
現金に対して負債が少ないほど、財務体質が良いと言えます。 負債について、特に注意するべきなのは「長期負債」です。 優良企業は、事業の投資を行う際は本業で稼ぐキャッシュを利用できるため、長期負債はあまり必要ありません。 資本に対して長期負債が大きい場合(20%以上ほど)、事業はあまり順調でないサインかもしれません。
また、貸借対照表に自社株(Treasury stock)がある場合、企業が株式を買い戻し、消化しないまま持ち続けていることを意味します。これは企業の純資産が減少することになります。 基本的には自社株を持っていることはよいことですが、自社株を持つことで純資産を減らしてROEを向上させる施策がとられることがあるのに注意しましょう。
固定資産について見てみましょう。固定資産は、工場など不動産が含まれます。かつてバフェットが買収したWrigleyは、固定資産が小さい企業でした。Wrigleyは、常に同じ製品を作り続けるだけで十分なキャッシュが得られたため、設備更新を頻繁にする必要がなかったのです。 同じような観点で、固定資産は小さい方が望ましいです。
最後に見ておくべきなのは優先株の有無です。優先株とは、通常の株式よりも優先的に配当金を受け取ることができる株式のことです。普通株は会社の支配権を表しますが、優先株は議決権はありません。また、会社が倒産した場合、優先株は普通株よりも優先的に配当金を受け取ることができます。通常、競争優位性のある企業は優先株を持つことはありません。優先株は株式ではありますが、実質上は負債としての性格が強いためです。
株価について
株価に対する考察は、上に挙げた4つの項目を踏まえて行います。
- 内在価値の評価を行なったか?
- 現在の時価総額は、内在価値より10%以上低いか?
- 利益剰余金1円につき株価を1円以上あげることができているか?
内在価値の評価は、DCF法を用いるのが一般的です。自分はフリーキャッシュフローに対してDCF法を適用し、内在価値としています。 内在価値を評価しておくのは非常に重要です。バリュエーションの評価としてPBRやPERを用いることはありますが、株価が割安かどうかを判断するためには内在価値の評価が必要です。 ただし、DCF法による評価はインプットとして用いる値によって結果が大きく変わります。 (特に割引率。自分は割引率としては事業の安全性を考慮しつつ、アメリカ10年債利回りであるUS10Yを用いることが多いですが、事業リスクが大きいと判断した場合は最大10%の割引率を使うことがあります) 様々な仮定のもとにDCF法を計算し、内在価値の値域を求めておくと良いと思います。
内在価値の評価を行なった後は、現在の時価総額が内在価値より10%以上低いかを確認します。 この10%というのは安全域(margin of safety)と呼ばれるものです。 この安全域を大きく取ることで、株価が下がったときにも安心して投資を継続することができます。 この安全域が投資の本質です。
最後の「利益剰余金1円につき株価を1円以上あげることができているか?」はOne Dollar Premiseと呼ばれるものです。例えば、昨期から今期にかけて利益剰余金が100円増えたとします。 このとき、株価が100円以上上昇しているならば、会社は利益剰余金をうまく活用して株価を上げることができたと言えます。利益剰余金は複利的に増加するため、その会社は株価も複利的に上昇するでしょう。
最後に
投資のチェックリストをまとめてきました。投資の調査を行った後は、自分の調査に自信があるか自問してみましょう。そこで自信がなかった場合は、いっそ投資をやめてしまうのが賢明です。 自分の調査が正しいと確信を持てる場合は、自信を持って投資しましょう。 投資後に株価が下がってしまっても、自分の調査に自信があるならば狼狽売りなどはせず、安心して株を保有し続けることができるはずです。